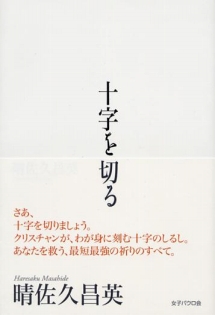すべての明かりを消した真暗闇から突然天に突き抜けるような、神父様の力強く美しい祈りの声でスタートした洗礼の式典は、予想をはるかに超えた幻想的で厳粛なミサに感動しました。
母の胎内にいる様な感じの温かさ、教会の皆様の心を尽くした最高のお世話、喜んでくださる微笑み、代親のシスターが折に触れ握り締めてくださる本当に温かい手の印象は忘れられない。何より10年も前に先に受洗し、家にあってもカトリックの話や、本の購入、教会への誘いと、陰の絶大な力添えをし続けた娘は、前夜に書いた喜びのカードを持参していて、式典後渡しながら抱きついてきた。
そのカードの「大切なママ…」と始まる文章に、私は産んだ子どもに私が再び誕生させてもらった…という思いと、導きの方向に共に歩いてくれた10年の道のりを思い心からうれしかった。心から申し訳なく思った。
娘が大学時代、講師としていらしていた40代の神父様の書かれた授業用の1枚のプリントの文章に強烈に心引かれました。ここまで謙虚に勇気を持って恐れず書かれる心根の純粋さに、母として受け入れ難い価値観に、時として闘うこともある生き方へ勇気の共感を覚えたこと。これが今この洗礼へと導かれた根底にあります。
「母になることは、ひとりのいのちを神様からあずかること」と確信させられた、当時港区にあった病院の高層の窓から、産まれた「いのち」の塊の娘を抱き、下を歩く人達を見て、この小さな重みこそ、すべての真実、嘘のない絶対の信頼そのもの!と何か天の国から下界を眺める心境だったことを、心の核心として実感したことを、はっきり思い出すことができます。
この核心とカトリックの洗礼は、一直線で結ばれていることを感じます。
毎月サンパウロ発行の「家庭の友」の1ページ目に欠かさず詩を掲載されておられる神父様の詩の中に「人間は宇宙の愛」という言葉があった。
私は本当にワクワクとうれしい気分で、宇宙を飛んでいるようなさわやかさを感じ、この世の出来事、悩み、恐れは「宇宙の愛は、人間にとってほんの石ころよ!」と大胆に心が据わった。神の子として宇宙に、親にゆだねることの天才!赤ちゃんのように楽々とした自由感!
5月から受講した入門講座でも、最初の2〜3回目の頃、心の中にサラサラと水の流れる音をはっきり認識したことを思い出します。とても不思議な感覚だったので神父様にその席で質問した。「それはカトリックの本質です」とおっしゃった。私のわからない感覚をこれほど明確に答えてくださり、正直スゴイ感性の人と思いました。目に見えないことを言葉で最高に納得できるように証明できる方だと。
そして、またある時は講座の話が「人間としてのありようの、普通で当たり前のことを話していらっしゃる」と感じた時、私はこの普通のことを、こんなに感動して聴いている自分の心の中の汚染を感じ、悲しくてならない思いがした時も「その普通が大切なこと…」とまたも明確な応答。
その後は自分の生きて来た道を振り返り、逆廻しにグルグル巻きになっているゼンマイが少しづつゆるむような、苦しいような気持ちの時もあった。
講座を休みひとりになって心を顧み、思い込みや人の言葉に支配され苦しい悲鳴を無視した自分が思い出された。そして汚い言葉でなく、本当に愛に溢れた神の言葉を「ミサ」で「講座」で繰り返す日々を重ねる体験の尊さ、大切さがはっきりわかった。
「ミサは完全!」とおっしゃる神父様のミサの時の気迫は、時に前列に座っていると切腹を思わせる責任を一身に引き受けた厳しい冷風(霊風)を感じる。
普段のリラックスされている時の姿との振幅はあまりにも大きい。「現状維持は死!」と説教でおっしゃる内面を伺い知ることは難しいが、毎週金曜日の夜受けた、夜間学校に通ったような1年近い講座の内容は、「やさしいことを深く、深いことを面白く」現実の「今」の問題を題材に、毎回楽しみになった。
叙階25周年の銀祝を迎えられた54才の神父様のことを初対面の人はほとんど30代〜40代と見間違う。20数年、毎夏、無人島(故郷とおっしゃる)で過ごされる古代人の生き残りのような感性の神父様。
どうか金祝まで今のまま生き残り続けて、「多くの人、いやすべての人を僕は救う!!」とおっしゃる気概を持ち続けてくださるよう、洗礼を授かった感謝の気持ちを込め、心よりお祈りをいたしております。