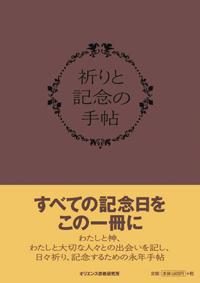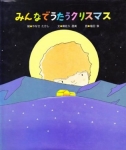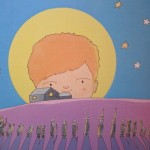桜井 琴乃(仮名)
洗礼式を終えて、最初に思ったことは、「ああ、ホッとした・・・。無事、洗礼の秘跡を授かることができて本当に良かった・・・」と。
洗礼式を前に家族(ペット)が入退院を繰り返し、手術をし、看病し、仕事はハードで夜中に出かけ、夜中に帰ってくる状態で、心身ともに限界状態でした。そして疲労と心労がたたり、もともと重い持病がある上に病気にかかり(それでも、ペットの治療費を稼ぐために休暇を取ることができずに仕事に行っては倒れの繰り返しで)志願式もリハーサルも出席することができませんでした。ですから、神父様をはじめ、入門係の皆さまには、私が本当に洗礼式に来られるのかと、本当に多大なご心配とご迷惑をおかけました。
さて、私が初めてこの多摩カトリック教会に訪れたのは、昨年の11月でした。それまでは、プロテスタントの教会に通ったり、別のカトリック教会で勉強を続けていました。その別の教会で多摩カトリック教会への誘いを受けて、今、私は神の子として生きることになりました。
そもそも教会という所に興味を持ち始めたのは、高校を卒業し、上京した先に教会がいくつかあり、もともと仏教の幼稚園に通っていたり、友人が熱心な仏教信者で、説教やお寺によく出向いて話を聞いたり、お寺にいたりしたことで、教会という所がどんな所なのか興味を持ったのが始まりでした。ふらっと教会に立ち寄り通ってみると、とても新鮮で興味はどんどん増していきました。そしてキリスト教の教えが心にスーッと入ってきたのです。今まで感じたことがなかった癒しがそこにありました。そして私もいつかクリスチャンになれたら・・・という思いが強くなりました。
しかし、そう思った理由が他にもあるのです。
実は、自分が生きていることに全く自信のなかった私は、常に生きていることに罪悪感を持っていました。
物心ついてから思春期まで褒められたことは一度もなく、母親に甘えたことも、ほとんど皆無でした。母親いわく、私がとても変わった子(周囲の人間も末恐ろしい、度し難いと言っていたそうです)だったという理由からずっと虐待(言葉と暴力)を受けてきました。常に「お前はゴミだ、害虫だ、ハイエナだ、霊付き子、殺してやる」と言われ続け、心と体の傷は今でも残っています。母はしょうがなかったと今でも言っています。私たち母子の関係は今でも良くはありません(昔ほどではありませんが・・・)。
私は幼い頃に父を会社の事故で亡くし、18歳になるまで母と暮らしていましたが、その間ずっと「私は愛されていない。いつか本当に殺されてしまうのではないか。だから、早く家を出よう」と考えていました。そう、まだ幼い私が本来考えるはずもないことのはずです。
晴佐久神父様は、ミサや入門講座でたびたび、「私たちはすでに赦されている、だから、もう大丈夫ですよ」とおっしゃっていました。私はその言葉にどれだけ救われたか。その言葉を聞いたとき、クリスチャンになれたらいいな、という思いから、「私、クリスチャンになる!」と決心がつきました。
洗礼式を終えて、私は神の子となり、今、自分にこう言い聞かせています。「もう大丈夫、私は赦されている。だから生きいてもいいの・・・」と。
ただ一つだけ悲しいのは、洗礼式を見に来てくれた母が、私がクリスチャンになったことに理解を示してくれないことです。洗礼を受けるにあたって、もちろん母に相談し、許しも得ました。しかし、本音は反対だったそうです。それを知ったのは、洗礼式を終えた後のことでした。私たち親子はこうもすれ違うのだと涙がこぼれました。
現在、母は「もう、虐待はしない、手を上げない」と決めているそうです。けれども、肉体的な暴力こそ受けてはいませんが、母の口から出る言葉は刺々しく私の心に突き刺さります。言葉の虐待を今も続けていることに、本人はまったく気付いていません。
私はそんな母を見て、少し不安を覚えています。「人はやはり変われないのか」と。「もう大丈夫、私は赦されている、だから生きていていいの・・・」心から私がそう思える日が本当に来るのか、そして、神の子となった私が、母を変えられることができるのかと・・・。
重い持病よりも、もっと重たい何かが私にのしかかります。
「もう、大丈夫、もう大丈夫」、そう、まるで呪文のように唱えながら、今日も十字を切っています。
そしていつか、私の心も体も「生きる強さを持つ」のだと。
今日より明日、明日より明後日・・・神の赦しと救いを受けながら・・・神を信じ、生きていくのだと決めたのですから。だから「もう、私は大丈夫」。ねっ、神様っ!