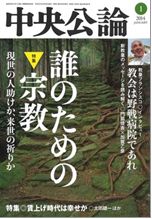先週、東京に45年ぶりの大雪が降りました。
聖堂前の聖母子像にも雪が積もり、親子でとっても素敵なロシアの帽子をかぶっていました。写真を載せましたのでご覧下さい。かわいいでしょう?(※1)
45年前の東京の大雪を、よく覚えています。そのころは東京都文京区在住、小学校5年生でした。膝まで隠れるほどの雪が降り、交通はすべてストップ、学校は休校となり、非日常に興奮する性格だったこともあって、はしゃぎまくったものです。
我が家のすぐ前に会社の庭のような広いスペースがあったために、そこは自然発生的に近所の子どもたちの雪合戦会場となりましたし、父親と日が落ちるまでかまくらを作ったのもいい思い出です。あの大雪は、ホントに楽しかった。
人の本性は、いくつになっても変わりません。今回も、次第に雪に埋もれていく街並みを眺めているだけで、気持ちは不思議に明るくなっていくのでした。
そういえば、翌日の日曜日、遅れた電車で教会にやって来た友人が言ってました。
「大雨の日はみんなイライラして、電車の中もギスギスしてるけど、大雪の日はみんなどことなく優しくて、電車の中がホンワカ暖かい」
たしかに雪は、天の使いのように、みんなの気持ちを穏やかにしてくれるのかもしれません。「みんな、もっと優しくなろうよ。そんなに怖い顔してないで、のんびりやろうよ」って感じに。
日曜日のミサに、ひとりの韓国人女性が来ていました。ワーキングホリデーで日本に来ている学生ということで、日本語がとても上手でした。その日の予定が雪で中止になったために、よし、今日はぜひ多摩教会へ行こう、と思い立ったそうです。
晴佐久神父の著作は、何作か翻訳されて韓国でも発売されているのですが、彼女によると普通の本屋さんでも売られていて、彼女は詩集「だいじょうぶだよ」(※2)に出会ってとても感銘を受けたとのこと。特にその中の「いいよ」という詩が大好きだということで、ぜひ日本に行ったら著者に会ってみたいと思っていたそうです。
彼女が気に入ってくれたフレーズは、「いいよ」の中のこんな部分です。
「君がいてくれれば/君でいてくれればいいよ/君は悪くない/なにひとつ悪くない/みんな君を大好きだから/君は君自身になっていいんだよ」
競争激しい韓国で、生き辛さを感じていたのでしょう。「それじゃダメだ、もっと頑張れ、今の君のままじゃ必要ない」、などと言われ続けてきたのかもしれません。心の奥では、「そんなあなたでいいよ」って言ってくれる人を、ずっと求めていたのではないでしょうか。 「この詩に救われました」というその目は、うるんでいました。いつも持ち歩いている、ハングル文字の「だいじょうぶだよ」にサインしたら、とっても喜んでくれました。
今の世の中、確かにイライラして、ギスギスしています。厳しい声で、ああしなくちゃダメだ、こうしちゃダメだと、ダメダメばかりで、「それでもいいよ」っていうあったかい心が見当たらない。責めあうばかり、必死になるばかりで、もっと発展しよう、もっと得しようと、世の中全体が過熱して制御不能に陥っているのではないでしょうか。
詩集「だいじょうぶだよ」には、「初雪」という詩も載っています。
「そうしてある日の夕方/街に雪が落ちてくる/毎日我を忘れたお祭りだったので/だれにも何の心構えもなく/みんなどうすればいいのかわからない(中略)子どものようにもはしゃげないし/平静を装うにはあまりに美しい/今年初めての雪/終わりのないゲームで発熱した街に/さあもうお帰りと/純白の鎮静剤が落ちてくる(後略)」
さて、そう書いている今日も、朝からまた雪が降っています。深夜まで降り続くとのこと。明日はちょうどこのニューズの印刷日ですが、果たして広報部の皆さんは来られるのでしょうか。
たまにはお休みしてもいいよ。
※【 参照 】
※1:「聖堂前の聖母子像にも雪が積もり・・・」 
・・・< 文中へ戻る >
※2:「詩集『だいじょうぶだよ』」
(参考)

・ 晴佐久昌英 著
・ 出版社:女子パウロ会
・ 128ページ
・ 単行本 (B6判 並製)
・ ISBN978-4-7896-0535-9
・ 初版発行:2001年4月25日
・ 18刷発行:2012年4月2日
・ 紹介:「星言葉」で多くの人々を励まし反響を及ぼした著者の、さらなる優しさと苦しみへの共感から生まれ出た詩の数々。「初雪」「病気になったら」「贈りもの」「クリスマスの夜は」など、32の福音詩を収録する。(「MARC」データベースより)
・ 詳細、ご購入は、以下のページなどからどうぞ
☆ 「女子パウロ会」
☆ 「 Amazon.co.jp 」(アマゾン)
・ 関連記事:「電子書籍「だいじょうぶだよ」配信記念講演会」
(「女子パウロ会ニュース」2012/02/13)
・・・< 文中へ戻る >