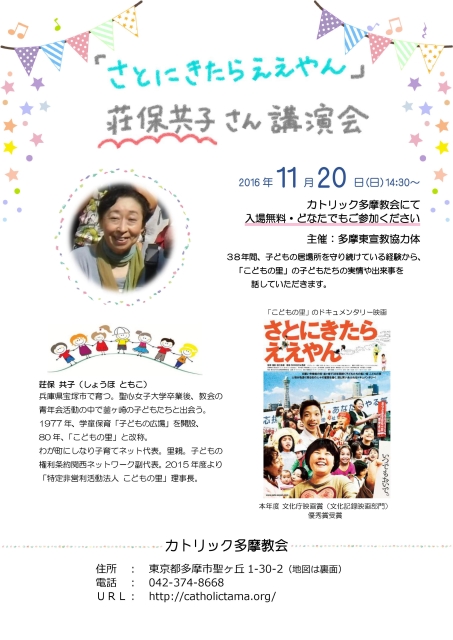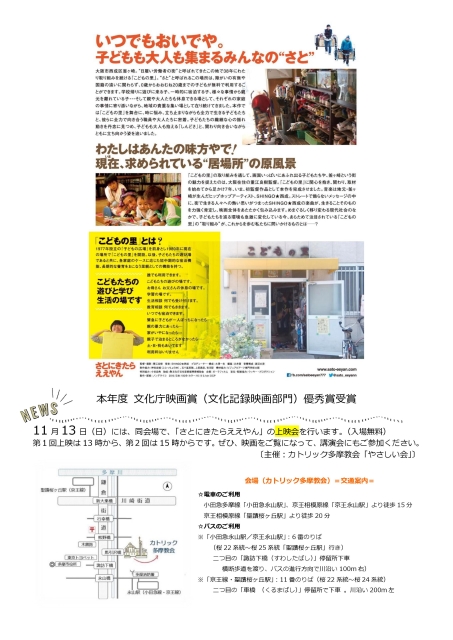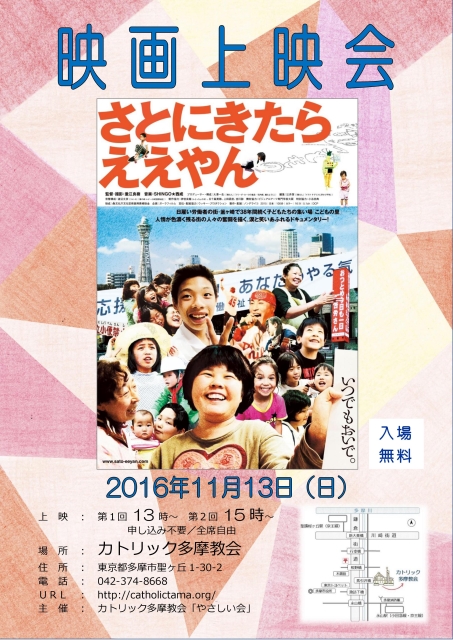「荒野のオアシス教会を目指して」
連載コラム「スローガンの実現に向かって」第71回
「全ては御手のなかに」 -婚姻の秘跡の更新-
「神が生涯を通して、お二人を守ってくださいますように。そして逆境にあっては慰めを与え、順境にあっては助けとなり、お二人の家庭を祝福で満たしてくださいますように」。司祭の祈りが響いた。「アーメン」と二人は唱和した。10月29日土曜日、多摩教会の夜のミサは終わり、聖堂は静寂に包まれた。間もなく、祭壇の前には豊島主任神父と祭壇奉仕をしてくださるTさん、そして私たち夫婦だけになった。私たちは今年結婚50周年を迎えるので、金婚の祝福を司祭にお願いしていた。それもささやかに質素に行いたいとお願いしていた。
この日を迎える一年前までは、「やがては巡ってくる50年」で、特別の思いも、何か記念行事をすることなど全く念頭になかった。しかし私は結婚して以降、子供の出産・育児から大人に成長して独立して行くまで、無我夢中で働き、頑張り続け、そして今日を迎えたのだ。今年は私も「シニアの集い」に招待される年になり、今日まで無事過ごせたのは妻をはじめ、実に多くの人々の支えによる賜物だ。この節目に、巣立って行った子供たち家族を招待して「感謝の会」をすることを思い立った。そしてその中のエンターテイメントに、結婚当時から、最近までの50年間を短編動画にして、皆に見てもらうことを思いついた。小中学生になる孫たちに、私たち祖父母の若い頃や、ママの生まれた頃を見るいい機会にしたい。皆どんな顔して見てくれるかも楽しみである。
私は子供のころから、カメラと撮影が好きで、社会人になって、当時普及していた8ミリ映画を趣味にしていた。押入れに仕舞い込んでいた古い8ミリフィルムを探し出した。ずっと仕舞っていた映写機も動くかどうか心配だったが、多少手入れをしたら、なんと20数年振りに動いた。当時フィルム会社にいた友人が、結婚式・披露宴など撮ってくれていた。それは、モノクロで鮮明さはまるでないし、音声も入ってない。子供の誕生や幼稚園の入園式、マイホームで初めて迎えた新年や、凧揚げ風景など、すっかり忘れていた当時の様子を再現した。音声がないのは寂しいので、各シーンに相応しいBGMを入れることにした。動画編集は週末しかなく、フィルムのデジタル変換、BGMの挿入に週末は深夜にまでかかった。こうしてパソコンで50年を18分で再生できるCD/ROMが出来上がった。
この動画編集を終え、私は言葉に表せない何か胸に迫ってくるものを感じた。50年の大きな時の流れの中に、なんと多くの人に支えられ励まされ歩んできたことか。その支えの中にあって今まで生かされている。ある修道会のR神父の言葉が蘇った。「神から自分に頂いた賜物を、生涯かけて完成させる。生涯かけても完成出来ないほど多くの賜物を頂いている。完成させる場は、職場であったり、台所であったりする」。
いつくしみの特別聖年の今年、私は今も現役を続け、妻は家事とパン焼きを楽しんでいる。離れている家族もそれぞれ平穏に暮らし、孫たちもタケノコのように成長している。
毎日繰り返される普段の生活が「今日こそ神がつくられた日」で、小さな秘蹟の更新だ。全てはいつくしみ深い御父の御手のなかに守られ、主が共に居てくださるオアシスだったのだ。