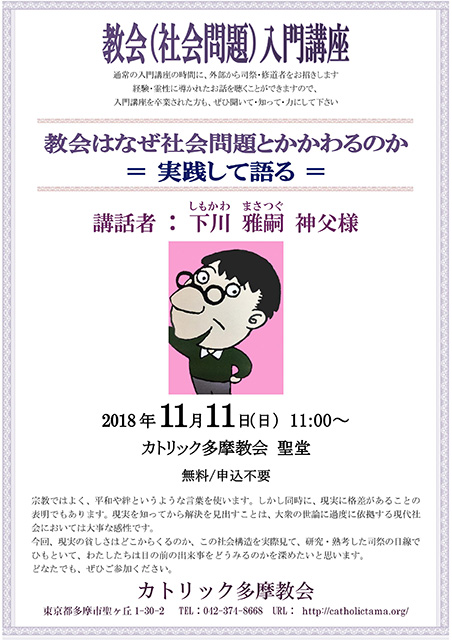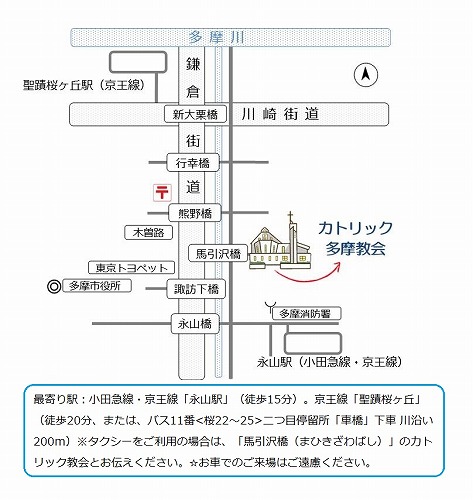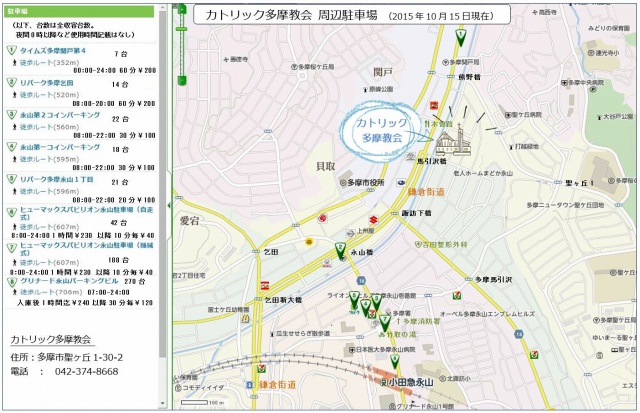= ウエルカムのサインをあなたからあなたに =
連載コラム「スローガンの実現に向かって」第94回
「Accueillir=受け入れる」
フランス生活に溶け込んできた頃、家の近くのミサに与った。そのとき « 献金 »の係をやってくれと頼まれたことを、今でも鮮明に覚えている。近くの住民しか来ないような小さな教会で、日本人の私に声をかけてくれたことがとっても嬉しかったのだ。この時ようやくフランスに受け入れられたように、ふと感じた。
私は2017年5月から1年半ほど、フランス・リヨンに暮らした。リヨンはフランスのローヌ・アルプ地方に位置し、他の都市への移動に利便性が優れた街である。カトリックの教会も多く、毎日曜日、どの教会のミサに与るか決めることは滞在中の楽しみの一つであった。その中で、Basilique Notre Dame de Fourvière=フルヴィエール大聖堂と、Église de Saint-Nizier de Lyon=サン・ニジエール教会が、いつも通うお気に入りの教会となった。フルヴィエール大聖堂は、ペストが流行した時代、リヨンを守ってくれたマリア様に感謝して建てられた教会である。丘の上にあるこの教会は、リヨンを見下ろして日々市民を守ってくれているのだ。いわば、リヨンのシンボルともいえる教会である。
渡仏して早速出会った文化の違い、それはミサで握手をすること。ミサに与り、主の平和の挨拶で「La paix du Christ=主の平和」と言いながら周りの方々と握手をする。当初は、今までお辞儀の文化の国にいたため、もちろん抵抗はあった。しかし、フランス人をはじめ現地の人々の握力がしっかりと強く感じ、それはまるでパワーをもらっているかのようで心地よかった。そしてミサ後には、教会の入り口の扉の前で司教様や神父様が待っていてくださって、「Bon dimanche !=良い日曜日を!」と挨拶を交わしながら握手をする。これがまた皆笑顔で挨拶をするので、今週もまた頑張ろう!という気持ちにさせてくれるのだ。「握手をする」ということは、お互いに受け入れ合おう、という気持ちの表れとも言えるのではないだろうか。そしてフルヴィエールの丘からリヨンの景色を一望して心を落ち着かせ、小道を通って旧市街へと出て、マルシェ(川沿いの露店の市場)で季節の果物を買って家路に着く。週の安息日である、休日モード全開なフランスの日曜日を存分に堪能する、というこの新しい習慣。私は週の中で一番と言っても過言ではないほどワクワクした。
最近では、サン・ニジエール教会へも足を運んでいた。この教会はいつもフォークソングの聖歌を歌う教会で、さらに子供の数も、とても多かった。硬い雰囲気のフルヴィエールとはまた趣が異なるこの教会で、大きな感動をした出来事がある。ある日、乳幼児洗礼式が行われた。まだ生まれて間もない赤ちゃんは、神父様の「父と子と聖霊の御名によって」という声に合わせて裸で洗礼盤に入れられる。不思議なことに、直前まで泣いていた赤ちゃんも聖水に浸かると泣き止む。式の終盤では白い衣を着せられた赤ちゃんを、フォークソングに合わせて、お父さんたちが私たち会衆に向かって高く上げた。これから新しい世界を知っていく赤ちゃんのぼーっとした顔、その光景がとても愛おしく、何か温かいものを感じた。
さらにこの教会では、ミサが始まってから、左隣の方と自己紹介をする時間が設けられている。例えば、なぜあなたは教会に来ているの? 誰のために祈っているの? といった類である。たまたま私の隣にいたマダムは、「いとこの病気が治るようにお祈りしているのよ」と答えた。こうした問いかけを受けて、私が思ったのは、1歳の時に洗礼を受けた私にとって、教会へ行くことは学校に行くこととほぼ同じだったな、ということである。日本では、教会にいる仲間と笑って話してご飯を食べる、それが私にとっての教会だった。このたった2分ほどの短い自己紹介なのに、いつの間にかお互いに打ち解けているのだ。ミサが終わった時には、自然と「Bon dimanche!」と口から出てくるものだから、教会って面白いな、楽しいな、と日々感じる。
しかし留学というものは、楽しいだけでは終わらない。日本では容易く行えることが、フランスでは非常に労力が要る。例えば、銀行口座を開いたり閉めるために、数日銀行に通ったり、授業中は自分の意見を20分ほど論理立てて発表したり、といった感じだ。自然と自己解決能力が鍛えられ、たくましい人間にならざるを得なかった。そんな生活で、教会は心の休まる場所となったのである。
「美食・芸術・素敵な街並み」というのが、所謂フランスのイメージかもしれないが、信仰の面でも十二分に堪能した生活となり、神様ありがとう、と思った。何よりも強く感じたことは、「受け入れる」ことによって自らの心が大きくなる、ということである。これは簡単そうだが、それでいて少し勇気の要るものかもしれない。しかし、ミサに与ると新しい輪の広がりを自分なりに感じ、教会を出てから「ハッピー!」と心の中で高揚しながらしばしば叫んでいたものだ。小さい私を受け入れてもらった喜びと、隣人を受け入れることで広がる楽しさを知った今、この気持ちを分かち合っていきたい。
神に感謝!