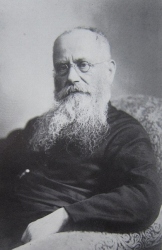「荒野のオアシス教会を目指して」
連載コラム「スローガンの実現に向かって」第68回
オアシスの水辺にたたずむ
暑い! 梅雨明けはいったいいつ?と思っていた7月半ばも過ぎた後半、やっと夏だ!と思いきや、この酷暑。冷夏より夏らしい夏は好きだけれど、それにしても暑い。しかし、この暑さの中、某ホテルの日本庭園を友人らと散策する機会があった。人工的ではあるけれど、所々に樹々があり丘があり、緑も多いせいか過ごしやすく風も通る。初老の方々も木陰の椅子に座り、話の花を咲かせていた。
友人が「ここは緑があっていいね~! やっぱり緑よね、オアシスだわ~」と、喜びの声をあげている。「オアシス・・・あ、原稿(これ)書かなきゃ」と私は心の中でつぶやきつつ聞いていた。
池のほとりに立ち、錦鯉のまぁるい口に不気味さを覚えつつ、この水があるから私達は生きられるんだなあとも、ぼんやり思う。
本当のオアシスでの水は、生死に関わる大きな存在。その水で、人も動物も植物も生きている。
私達の、私の信仰を振り返る。キリストとの出会い、生きていく中でオアシスを知り、水をいただいた。その水に生かされていることに思いを向ける。日々の暮らし・・・主の御心にかなってる? 非常に遠い所を歩んでいるという気持ちの方が強い。弱さと不安、恐れに打ちひしがれることの多さ。だけれど、だからこそ水辺にたたずみ、水をいただく。渇きを癒やしていただく。
今春、高齢の母がこの世での生を終えた。感情でぶつかる母娘関係でもあったけれど、根底にあるのは愛おしさだった。聖書を学んだこともなく、唯一、昨夏の入院手術の前後、ベッドの傍らで聖書を読む(主に詩編)という行動を夫がしてくれていた。娘である私は、気持ちはあっても動けないことを痛感もしていた。私がしたところで素直に聴けるのか、聴こうとするのか? しかし私の懸念を払拭するが如く、母は真摯に耳を傾け心を向けてくれた。気丈で自立心の強い母は、今までそんな姿を見せたことがなく、それだけ緊張し、心細さを感じていることも改めて実感としてわかり、その姿に何とも言えない気持ちも感じた。
その母に救いの水を渡したい。無理だろうか? 母だけでなく、他の者に受け入れられるのか? 勇気を持って切り出した。「母の魂の救いのために、洗礼を授けたい」と。拍子抜けするほど、あっさり受け入れられ、意識朦朧の母に水を垂らす。愚行多き私に「また、何をやっているんだか」と、きっと思っているだろうと思いながら。
夕方、主の祝福と言っていいと思うくらい、久し振りに美しい夕焼けを見た。日中の曇天を貫く光の強さと美しさに、茫然としながら「神様、感謝します」という言葉が心に浮かんだ。甘く、ゆるい信仰なれど、ここぞという時にいつも助けてくださる主。その主に感謝して、主の泉、オアシスの水辺に、また時折たたずみたい。